
人はたいてい箱を持っている。そして、その箱の中に大切なものや捨てられないものをしまい込んでいる。
持ち主にとって、それがどんな宝物であっても、時の経過とともにそれは日常に埋没するか、忘れ去られていく。
スー・ ヘイドゥの「箱って?」は、箱の中にしまい込まれたまま、ともすると忘れられゆく物語を、箱の持ち主とのコミュニケーションの中で、改めて見つめ直すプロ ジェクトである。人通りの多い商店街からほんの少し横丁に入った、甘味処の静かな待合いスペースにしつらえた小さなテントの中で、 1 時間もの時間をかけ、ゆったりと心をもみほぐしながら互いの話を打ち明け合う。
参 加者は用意していった自分の物語を彼女に話す。そして、ヘイドゥは巧みに、本人も忘れていた記憶の引き出しを次々と開けていく。参加者にとって予期せぬ贈 り物は、ヘイドゥがプレゼントしてくれる箱とそれにまつわるストーリーである。見知らぬ箱に触れ、彼女自身のストーリーを聞き、参加者は突然思いもよらな い他者の人生をかいま見る。自分とは異なる時代、異なる場所に生きてきた人たちの確かな存在、生きる営みをまるで映画のように想像するのである。その体験 のあとでは、参加者自らが彼女に話したストーリーも、まるで他者のことのように感じられる。自分自身の過去を、一気に鳥瞰できる瞬間である。
それはきわめて不思議な体験だ。
箱 そのものが持っているエキゾティックな雰囲気やその中に残されていたものが発するメッセージ、そしてその箱の持ち主のストーリーは、自分自身の箱とストー リーの対価として与えられたものである。参加者はテントを出たあとも、ヘイドゥと自らのストーリーを幾度となく反芻する。ヘイドゥが行った見えない価値の 交換は、アーティストと参加者の心を強く結びつけたのである。
そして、価値を交換する「商い」の本質がどのようなものであるのかを、わたしたちに提示しても見せた。
送別会の夜、プロジェクトに参加してくださった商店街の方々が、お別れのプレゼントに持参してくれた箱の中には、長い間『商い』を営々と行ってきた人々ならではの心遣いがつまっていたことを報告しておきたい。
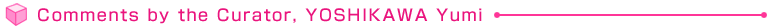
Most people own boxes which they might use to store precious objects or, alternatively, things they want to throw away, but somehow cannot bring themselves to.
No matter how important or invaluable these objects might be, they often end up buried and forgotten as day after hectic-day passes by.
Sue Hajdu's project, HAKOtte? aimed to salvage and bring us face-to-face once again with these things through a process of communication between artist and participant. HAKOtte? took place in a quiet space on a side street off the busy shopping street of Ichibancho 4-chome in Sendai. Sitting inside a small marquee these two people were involved in an intimate dialogue, often taking over an hour, slowly opening up their hearts to each other.
Participants told Hajdu the stories they had prepared, while she sophisticatedly opened the drawers of their memory, which even the participants themselves had sometimes forgotten about. In return they received a box from the artist, sometimes unexpectedly. Laying eyes on an unfamiliar box, hearing the artist's story about it, they found themselves looking at the life of somebody they had not ever dreamt about, imagining people in a time and place totally different from theirs?an experience akin to watching a film. In this moment they got a strangely objective overview of their own lives?an experience that is highly unique.
In return for the their boxes and stories, participants came away with a strange new box, the contents that the artist or previous owner might have left in the box, and the story told by the artist. After leaving the tent, they will find themselves going over Hajdu's and their own stories again and again. The artist's exchange of invisible value has certainly connected herself and the participants on a deeper level, a phenomenon that demonstrates so vividly the essence of trading?an exchange of values.
As a final comment I would like to note that on the night of the HAKOtte? closing party, people from the shopping street?both those who participated the project and those who did not?brought boxes for the artist. These boxes were full not only of their farewell presents but also of their regards and considerations that were so characteristic of those who have been engaged in trading for such a long time.
この文章は、オーストラリアのブンダノンにおいてアーティスト・イン・レジデンスをしている際に書かれたものである。文章を書くことに集中できる貴重な機会を私に与えてくれた The Bundanon Trust Artist in Residence Program に感謝の意を表したい。
人々が自発的に参加してくることを必要とするプロジェクトには、常にリスクがつきまとう。アーティストやキュレーターが事前に人々の反応を予測してみたところで、実際にプロジェクトが始まるまでは何一つとして確かなことはないのだ。
不安と期待が入り混じる中、私は「箱って?」の初日を迎えた。私の意図は、プロジェクトのフライヤーや広報によって、どのくらい伝わっているのだろうか?仙台の人々は「分かって」くれるのだろうか?彼らは「箱って?」を単なる箱の交換として見るだろうか、それとも本能的にこのプロジェクトのより深い意味 ? 物質的なものを超えたところにある価値の交換 ? を理解してくれるだろうか?
このプロジェクトの成功は、 22 人の参加者それぞれの冒険心、オープンな心、そして誠実さによってもたらされた。プロジェクトが始まり、最初の数人の参加者と話すと、それまでの私の心配はもう消え去っていた。彼らが持ってきた箱には、いい加減だったりかたちばかりのところは全くなく、どの箱にも彼らの人生に対して誠実で、重要なストーリーが入っていたのだ。そして彼らがそのストーリーを私に語ってくれた時、私はそのストーリーの「キー・ポイント」を見つけることができた。それは参加者に、他のどの箱でもなくこの箱を選ばせた心理的な要素だ。彼らのストーリーが、このウェブサイトの記録からも上手く伝わることを願っている。
またとても強く心に残っているのは、ほとんどの参加者に変化が起こっていくのをこの目で見ることができたということだ。このようなプロジェクトなので、参加者はみな張りつめた好奇心とともにプロジェクトの会場にやってきた。みなプロジェクトの基本的な内容は分かっていたのだが、この交換がどのように行われるのかについては明らかに確信を持てていなかった。それが、私たちがともに時間を過ごすにつれて参加者の表情が段々と変わり、最後には晴れやかな顔になって目が輝いているのがはっきりとわかった。もちろん、人はみな自分について話すのが好きだし、しっかりと話を聞いてもらうのが好きなものだ。だが、この変化はそういった単なるナルシシズムを超えた何か、このプロジェクトの核心であったある種の「交換」が、参加者も私もそうとは意識しないままに、確かに行われたことを示していた。それぞれの交換において何かしら開放されるもの、そして受け取られるものがあり、このような交流は大変素晴らしいものだった。
……………………..
プロジェクトの会場となったテントやその中で使用した小道具はシンプルでミニマルなものであり、ほとんどニュートラルと言ってもよいようなものだったが、みなきちんと考えて選ばれている。テーブルと二脚のいす、というのは人と人とのやりとりにおいて最も一般的なセッティングだ。お茶は寒い時に体を温めてくれるし、喉も渇かない。しかし、お茶にはこの他にも隠れた意味があった。はるかな昔から、お茶というのはコミュニケーションを円滑にするツールだったのだ。私たちは客を迎え、語り合い、お茶を注いで飲む。またお茶とお菓子があること自体が簡単な話題にもなり、実際に話し始める前に私たちの緊張を和らげるのにも役立った。
もちろんこれらは日本では当たり前のことであり、ここでは日本の社会におけるお茶の役割を分析するのが目的ではない。しかし箱の存在と同じように、このプロジェクトはこのお茶の存在なしでは成功しなかったであろうということは述べておきたい。小道具というのは大事なものだ。
参加者の一人の女性はこのプロジェクトの意図や仕組みについてとてもよく理解していて、まさにこのお茶というものが現在の日本社会でどのような状態なのかについて私に話してくれた。お茶は日本中どこでも自動販売機で売られており、乾いた喉を潤すという機能的な要素しか持たない液体になってしまった。お茶というものが本来持っているコミュニケーションを円滑にするという役割、儀式的な要素は少しずつなくなっているのだ。
……………………..
「箱って?」はアーティスティックな要素や個人的な要素、さまざまなものから着想を得た。そのひとつは私が今年の二月にした大掃除だ。七年間のうちに積み重なった、自分自身でも忘れていたようなものたちを整理しているうちに、沢山の箱が出てきたのだ。私はそれらを捨てたり整理したりして、新しいプラスチックケースを買い、自分の人生をそこに整頓しなおした。そしてその時、自分がいかに箱というもの、それが私たちの人生の中で果たす様々な役割、それが様々な意味で私たちの考え方やあり方のメタファーであることが好きだったかということに気がついたのだ。私は他の人々の暮らしや考え方の中で、箱がどんな役割を果たしているのか知りたくなった。
しかし、今考えると無理もないことなのだが、この点に限っては今回のプロジェクトで得られたところは少なかった。箱の愛好家にはほとんど会わなかったし、それどころか仙台の人々の多くは ? 私は信じなかったが ? 箱を持っていない、または使っていないなどと言っていたのだ。商店街である一番町四丁目においてすら、各店舗にプロジェクトの説明をしてまわっている時には多くの人が箱なんて持っていないと言っていた。そう言っている彼らのまさにすぐ後ろの棚には実に魅力的な箱が山積みになっているのに、である。私たちは、自分自身について何と無知なことだろう!
大掃除が終わった時点では、私は「箱って?」を参加者の箱を受け取るための手段としてしか考えていなかった。箱は燃やしてしまうか、こういうものをもっと切実にほしがっているホームレスの人たちにあげてしまおうかと思っていたのだ。せっかく参加者の人生を箱一つ分整理することができるというのに、その分私の方にその箱を積み上げていったいどうしようと言うのだろう?
しかしプロジェクトの二日目までには、私にはそんなことはとてもできないという事が明らかになっていた。参加者たちは、ほとんどが自分の箱をあげてしまうつもりでやってきたが * 、誰一人として自分の箱がその後どうなるのかは聞いてこなかった。彼らの箱とストーリーについて私は信頼されていたのだ。そしてどの箱も ? 今は分かるのだが ? 参加者ひとりひとりの人生にあまりに深く関わったものだった。
価値の交換としての「商い」という行為のここまでの社会性は、自分の想像の「外」にあり気がつくと私はある関係の「内」に捕らえられていた。
「箱って?」のテントは一番町四丁目から横丁に入ったところにセットアップされ、まずそのこと自体が私やプロジェクトのスタッフたちと、その場所の商業コミュニティとのコミュニケーションを生んだ。私たちはその場所の所有者である彦いちの社長さんと毎日あいさつをし、プロジェクトの小道具や弁当を近くの店で買った。私たちはこのプロジェクトについての告知と説明をするために多くの商店をまわって商店主と話をし、そのうちの何人かは箱とストーリーを持ってプロジェクトに参加してくれた。
このプロジェクトを ART 仙台場所の目的とその会場のためだけにつくりあげたということも自分にとって重要な要素だった。一番町四丁目は、活性化の術を探している商店街だ。そこでのコミュニティを定義するとしたら「ある同じ場所で商売を営む商店主たち」ということになるだろうか。しかし「箱って?」を通して、彼らにとってのコミュニティというものはこのような一般的な定義よりも遥かに深いところにあるということが分かった。二週間の仙台滞在の間、毎日一番町四丁目の人たちと触れ合うことで、ローカルな歴史(仙台四郎の話など)、いがみ合い、対立、欲望などについても聞くことができ、私にとって一番町四丁目というのは「人々を結びつけ、コミュニティとして存在させる、複雑な人間関係の網の目」というものが表現されている場所となった。このプロジェクトは、確かにそこにあるのだけれども隠れている、という何かに光をあてることになった。より小さなスケールで箱たちがそうしたように。
ある日、キュレーターがプロジェクトの会場へと横丁に入ってきたところで、ちょうどプロジェクトへの参加が終わって帰るところのある商店主とすれ違った。彼女は私のところに走ってきて、彼の顔が今までみたこともないように輝いていて「別人のようだった」と教えてくれた。「箱って?」は親密さが必要で時間がかかるものであり、その性質上どうしても少数の人間にしかダイレクトには届かないものなので、これは私にとって素晴らしいニュースだった。このプロジェクトは規模として大きくはなかったが、そのぶん深いものだったということだ。
プロジェクトに参加することを通して参加者たちが変わっていくのを見るのは、それだけでこのプロジェクトをやってよかったと思えるものだったが、この商店主の変化について私が特に嬉しかったのは、彼が一番町四丁目商店街の一員だったからだ。プロジェクトのクロージング・パーティに集まってくれた商店主たちの様子を見ても、このプロジェクトがこのコミュニティに何らかのクリエイティブで、感情の動きを伴う変化を与えたように見えた。また私は後にプロジェクトのスタッフから、一部の商店主だけではなく一番町四丁目全体の考え方が ART 仙台場所によって変化したようだと聞いた。これはグローバライゼーションの中で画一的な商業のあり方にのまれることなく、自分たちのあり方を見直し、自分たちらしさを意識的に見出そうとしているこの商店街、そしてこの地域にとってとても重要なことだ。
「箱って?」の目的の一つは、「特別なことは何もしない」ということの精神的価値を追求することだった。一時間、見知らぬ人と面と向かって座り、直接同じ空間を共有する。話をして、微笑み、交渉をし、与え、助け合う。このプロジェクトの結果を見ると、私たちはどうやらまだこの直接的な人と人との交わりを楽しむことができ、「特別なことは何もしない」ということの精神的価値は高い、と言えるのではないだろうか。
* 参加者のうち何人かは彼らが持ってきた箱を手放すことができなかった、というのはこの場合あまり問題ではない。大事なのは「箱は手放す」ということが一般的な参加者の意識になっていたということで、もし箱を手放さないということになっていたら、参加者の意識はまた違ってものになっていただろう。
c Sue Hajdu, Bundanon, June, 2008
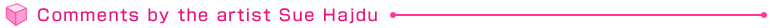
These reflections were written during the artist's residency at Bundanon, Australia. Many thanks to The Bundanon Trust Artist in Residence Program for this invaluable opportunity for focused work.
All projects that are reliant on spontaneous public participation come with a degree of risk. While the artist or curator can estimate beforehand what the most likely reactions and responses will be, nothing is certain until the project goes live.
With nervous anticipation I launched the first day of the HAKOtte? project. To what extent had my intentions been successfully communicated by the project fliers and publicity activities? Would the public ‘get it'? Would they see HAKOtte? simply as an exchange of boxes, or would they instinctively understand the greater meaning, the exchange of value beyond objects or artifacts?
I owe the success of this project to the spirit of adventure, openness and sincerity of each of the twenty-two participants. After interacting with the first few participants, my worries disappeared. There was not a hint of anything arbitrary or token about the boxes that were brought to me, and each box contained a story that was genuine and significant in that person's life. As each participant related his or her story to me, I was able to identify the ‘key point' of the story?the psychological motivation for bringing this particular box to the project. I hope that I have relayed these stories successfully on this website.
Also absolutely poignant for me was being able to watch the transformation that occurred in most participants. Inevitably, everyone arrived at the marquee with a tense curiosity. While they knew the basic premise of the project, they were nevertheless evidently unsure of exactly how this exchange would transpire. Through the course of our time together, participants' expressions gradually changed, until at one point I saw their faces glowing, their eyes shining. Of course, most people like to speak about themselves and everyone likes to be listened to attentively. But this transformation indicated something bigger than just the narcissism of the ego. It indicated that the kind of exchange that was at the core of this project had indeed occurred, even if the participant and I were not yet conscious of that fact. In each case something was released, something was received. And this kind of exchange is a joyful experience.
……………………..
My setting and my props were simple and stripped back to the minimum, almost to the point of neutrality, but they had been carefully orchestrated. A table and two chairs is the most generic setting of social exchange. Drinking tea would keep us warm in case of cold weather, hydrated in case of thirst. Tea, however, had a more secret mission to perform. Since time immemorial, it has been a basic facilitator of human exchange?we receive guests, we chat about pleasantries, we pour and sip tea. The tea and the snacks served also became a talking point that could release nervous tension on both sides before the real talking started.
Of course none of this is a mystery in Japan and it was not my aim here to analyze or add to the historical role of tea in Japanese society. It's worth noting though, that this project probably would not have succeeded without the tea, just as it could not have done so without the boxes. People need props.
One of the female participants in HAKOtte? was highly conscious of the dynamics of the project and commented specifically about the present state of tea in Japanese society. Tea is sold these days in vending machines across Japan. It has become banally functional: a liquid to relieve the thirst, its role as social mediator, as object of ritual, slowly fading away.
……………………..
The HAKOtte? project arose from various sources, artistic and personal. One of them was a huge spring-cleaning that I did in February this year, sorting through forgotten piles of things from the last 7 years. Boxes appeared, boxes were thrown out, boxes were sorted and re-arranged. I bought many new plastic storage boxes to stack and re-organize my life into. I realized, once again, how much I adore and enjoy boxes, and the various functions they have in our lives; also, the various ways they operate as metaphors for human activities or thinking. I was curious to find out more about how boxes function in other people's lives and psychology.
This project yielded little in that regard, which, on reflection, is not so surprising. I met few professed box-lovers. In fact, many Sendai people claimed not to own or use boxes. I was not convinced. Even in Ichiban-cho 4-chome, as we were informing shopkeepers about the project, many denied owning any boxes. The curator and I could not help making an ironic note of the dozens of enticing boxes arranged on office shelves at the rear of each shop, just behind the shopkeeper's back. How much of our own lives is invisible to us!
In the aftermath of my spring-cleaning, my plan with HAKOtte? was to only act as a conduit for the boxes I received. I proposed for the boxes to be burnt, or passed on to homeless people who might have more immediate uses for them. Why repeat clutter and accumulation in my own life, when the project had already succeeded in moving one item of clutter from the participant's life?
By day 2, however, it was undeniably apparent that I was not emotionally capable of this. For the participants themselves, most came prepared to give their boxes away.* Yet, not a single participant inquired as to what the fate of their box would be. I had been entrusted with boxes and stories in good faith. There was something much too personal I now knew about each box.
I was caught out by the social face of trading.
I was caught in.
The HAKOtte? marquee was set up on a side street off Ichiban-cho 4-chome, and this very fact brought myself and the project team into interaction with the local business community. We exchanged daily greetings with the owner of Hiko-ichi (the Japanese sweets tea-house opposite the marquee), we bought items for the project or our bento-box lunches from local shops. We had visited many of the shopkeepers to inform them about the project and several of these decided to bring boxes and stories to HAKOtte?
Making the HAKOtte? project specific to the aims and location of Art Sendai-basho had of course been important to me. Ichiban-cho 4-chome is a trading street that is trying to find a means to revitalize itself. It might define its sense of community as ‘a group of shopkeepers doing business in a fixed location'. However, through HAKOtte? I was able to perceive a notion of community lying deeper than such a standard definition. My two-week stay in Sendai, each day interacting with people from the Ichiban-cho area, allowed me to hear about local histories (such as the story of Sendai Shiro), antagonisms, conflicts, desires. Ichiban-cho 4-chome came to represent for me a complex web of human relationships through which people are bound together. The project brought to the fore what is there, but hidden, just as the boxes did on a micro-scale.
One day the curator was walking into our side street just as one of the shopkeepers was leaving the HAKOtte? booth. She raced over to tell me that she had seen his face beaming like never before. He was ‘another person'. This was great news, as HAKOtte? was an intimate and time-consuming project that was only ever going to directly reach a small group of people. Within the context of Art Sendai-basho and its audience, HAKOtte? was narrow, but deep.
It was rewarding to witness the transformative effect of HAKOtte? on any individual, but I was particularly pleased that this person had been a member of the 4-chome shopkeeper community. The mood of the shopkeepers who got together for the closing party of my project was also indicative that HAKOtte? had had a creative and emotional impact in this community. I later heard from members of my project team that the mood all over Ichiban-cho 4-chome had been very much transformed by Art Sendai-basho. This is significant for a community and precinct that is searching to re-define itself, to consciously become distinct, rather than fading into the continuum of a globalized shopping experience.
One of the aims of HAKOtte? had been to explore the soul-value of “not doing much”. Sitting for an hour with a stranger?directly there: face-to-face?speaking, smiling, negotiating, giving, reciprocating. It appears that we humans do indeed still enjoy these direct, physical interactions and that the soul-value of ‘not doing much' is indeed high.
*It did not matter very much that some participants could not part with their boxes, what mattered was that this was a standard expectation of this project. Participants would not have come to the project with the same sense of a border to be crossed if they knew that their boxes were not going to leave them forever.
c Sue Hajdu, Bundanon, June, 2008


